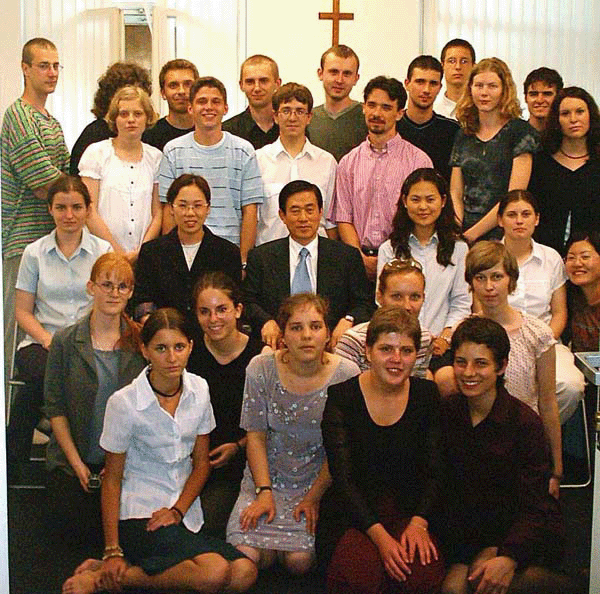1. 聖 霊 にあって享受する自由と 歓 喜
張ダビデ牧師が強調するパウロ使徒のローマ書8章は、聖書全体の中でも福音の真髄を最も美しく荘厳に表現している章であり、福音理解の核心的な鍵といえる。特にローマ書8章は「聖霊にあって享受するキリスト者の自由と歓喜の生活」を示す代表的な本文として、張ダビデ牧師は、この御言葉こそ、罪と死の支配から解放された聖徒たちがいかに大きな喜びと希望を得ることができるかをよく示していると語る。
まず、現代の聖書には章と節の区分があるが、本来の聖書にはそのような区分がなかった点に注意すべきである。したがって、ローマ書7章と8章を切り離してではなく、連続したメッセージとして見ると、私たちが経験する内的葛藤と、生まれ変わった者たちの霊的自由がより鮮明に理解できる。ローマ書7章23節から24節は、救われた者であっても深刻な内面の分裂と苦しみを経験する現実を示している。
「わたしの肢体のうちには別の律法があって、それがわたしの心の律法と戦い、わたしの肢体のうちにある罪の律法によってわたしを捕虜にしているのを見る。(ロマ7:23)
この本文について張ダビデ牧師は、すでに救われ罪赦しを受けた者でも、依然として肉に属する問題のために葛藤を経験する点に注目する。すなわち、救い(義と認められること)を受けた状態ではあるが、同時に聖化という進行過程にあるゆえ、「すでに」と「まだ」の間で深刻な内面的矛盾が生じるのは避けられないというのである。パウロは7章でこのような苦悩を吐露しつつ、ローマ書8章においてついに聖霊によってもたらされる解放と喜びを宣言する。
ローマ書8章の最大のテーマの一つは「聖霊にある生活」である。パウロが8章全体を通して提示するメッセージを整理すると、救われた聖徒たちがどのように罪と死の支配から解放されて自由に生きることができるのか、そしてその自由がどのような歓喜と力を生むのかを説明している。張ダビデ牧師はこれを「ぶどう酒にたとえられる聖霊に酔う生活」と呼ぶ。それは水がぶどう酒に変わるように、聖霊のみわざによって私たちの生活が全面的に変化する姿を象徴している。いったん変えられた存在が、再び以前の状態に戻ることがないように、救われた聖徒もまた原罪の支配から離れ、栄光へと進んでいくというのである。
しかしここで注目すべき点は、原罪が赦されても依然として私たちの内に残る「習慣的な罪」あるいは「自発的な罪」が存在するという事実だ。張ダビデ牧師はこれを「すでにぶどう酒となったが、その中に水が混ざって薄くなっている状態」にたとえて説明する。聖霊によって新生し聖なる者とされたとしても、過去の罪的な習慣が私たちの内面に働き続けるため、聖化の過程でこれを洗い清める作業が欠かせないというのである。
この点で、しばしば混同されるのがエレミヤ書2章22節とイザヤ書1章18節の間にある緊張感である。エレミヤ書では「たとえ灰汁で自分を洗い、多くの石鹸を用いても、あなたの咎はわたしの前にそのままだ」と述べ、イザヤ書では「たとえあなたがたの罪が緋のようでも雪のように白くなる」と宣言している。張ダビデ牧師は「これら二つの預言は互いに矛盾しているのではなく、人間の力では罪を完全に洗い落とすことは決してできないが、ただキリストが私たちの罪を代償されたゆえに、神の恵みによって完全に洗われることができる」という救済論的真理を指摘する。
これをより具体的に理解するためには「原罪」と「自発的な罪」を区別しなければならない。ローマ書5章でパウロ使徒は、アダムから始まる普遍的かつ連帯的な罪の問題が、イエス・キリストの贖いによって断ち切られたことを語っている。これが「原罪の赦し」であり、義認(Justification)として説明される「地位の変化」である。張ダビデ牧師は、この地位の変化こそが私たちの過去とは全く異なる運命をもたらすのだと強調する。もはやアダムのうちで支配されていた「死の権勢」はイエス・キリストによって撤廃され、実際にイエスを信じて新生した者たちの生活において「七つの呪い」のような運命的な懲らしめはもはや作用しないというのである。
だが、だからといって、罪との戦いから完全に解放されたことを即意味するわけではない。なぜなら私たちの内には「習慣的な罪」、すなわち自発的な罪が依然として残っており、それが私たちの歩みを妨げるからだ。張ダビデ牧師はこれを「本格的な戦争は終わったが、掃討戦が残っている」とたとえる。十字架と復活によってすでに大きな戦いでは勝利を得たが、日常における小さな戦闘は続いているというわけだ。だからといって、これら小さな戦闘は掃討戦である以上、結果はすでに決まっている。しかし掃討戦をおろそかにすると、その残党が再び私たちを苦しめ、聖なる道を妨げる可能性がある。
そこでイエスが最後の晩餐の中で弟子たちの足を洗われた場面(ヨハネ13章)を思い起こす必要がある。すでに全身がきよい者でも、歩き回るうちに足についたほこりは洗わなければならないように、救われた者も日常の中で犯す自発的な罪を絶えず洗い清めていかなければならないというのである。張ダビデ牧師はこの過程を「聖霊にあって行う自己省察と悔い改め」の過程と見る。このような聖化の訓練は、私たちがすでに得た義認の確信を揺るがすものではなく、むしろさらに強固にする恵みの手段でもある。
結局、罪に対する私たちの態度は、二つの側面を同時に抱かなければならない。一つは「キリストがすでに大きな戦いに勝利された」という勝利の観点である。もう一つは「残された戦いである掃討戦を私たちがなおざりにしてはならない」という緊張感である。張ダビデ牧師は神学者たちの研究と実際の信仰生活の両面において、人間が罪に対処するとき、この二重的視点を失うと極端に走りがちだと警告する。すなわち、「すでに罪は完全になくなったのだから勝手に生きてよい」という勘違いをするか、逆に「私たちの内にはまだ罪が残っているのだから救いの確信などあるはずがない」と落胆する態度を戒めなければならないということだ。
このようなバランスのとれた理解のもとで、ローマ書8章が私たちに示す第一の核心メッセージは、「聖霊にあっての完全な自由と歓喜は、実際に経験し得る現実である」という点だ。パウロはイエスにある者には決して罪に定められることがなく、いのちの御霊の法則が罪と死の法則から解放したと宣言する(ロマ8:1-2)。ここで私たちは法的身分が変わったことに伴う実質的な自由を享受できると確信する。
張ダビデ牧師は、ローマ書8章14節から17節を通して、この自由は決して抽象的な概念ではなく、「神の子ども」とされた者が「聖霊にあって」アバ父と呼び親密に交わる中で得る具体的な喜びと栄光として現れるのだと強調する。子どもとされた者は神の相続人であり、キリストとともに共同相続人となるゆえに、この地上でどのような苦難があろうとも、その苦難はやがて来る栄光とは比べものにならないことを悟る。これは単に頭で理解する真理ではなく、聖霊が私たちの内で直接証してくださる内面的な確信でもある。
さらに18節から30節に及ぶ、いわゆる「宇宙的回復」と「生ける者の復活」に関する教えは、このような自由が個人的・霊的次元を超えて、被造物の世界全体へ拡張される事実を示している。すべての被造物がうめきつつ産みの苦しみをしているのは、やがて現れる神の子どもたちの栄光のゆえにともに回復されることを待ち望んでいるからだ(ロマ8:19-22)。ここでパウロは人類を含む宇宙的な再創造のビジョンを提示する。張ダビデ牧師はこれについて、「新天新地を先取りする聖徒たちが聖霊にあって享受する自由は、個人の内的平安にとどまらず、歴史を変革する原動力となる」と説明する。
張ダビデ牧師は、この点を創世記9章のノアの物語に結びつけ、大洪水の裁きの後、新しい地、すなわち新天新地(new heaven and new earth)に下り立ったノアがブドウの木を植えてぶどう酒を飲み、その自由と喜びを味わったことをたとえとして用いる。ノアが酔って裸になった姿は、エデンの園で堕落前のアダムとエバが裸であっても恥ずかしくなかった様子と通じると語る。これは「罪以前の純粋さ」、あるいは「聖霊にあって享受する聖なる喜び」を象徴する。
ここでぶどう酒は、聖霊の象徴であり、罪の赦しと新しいいのちの喜びを意味する。イエスがカナの婚礼で水をぶどう酒に変えられた出来事がこれをあらかじめ示しており、使徒行伝2章でペテロ使徒と弟子たちが聖霊を受けた後に「新しいぶどう酒に酔っている」と非難された場面もまた同じ文脈にある。すなわち、聖霊降臨によって予告されていた新しいぶどう酒が実際に注がれ、これこそ旧約の預言(ヨエル2章など)が成就した結果であると、張ダビデ牧師は強調する。
したがって、ローマ書8章が示す自由は「水のような存在」が「ぶどう酒」に変えられ、再び元に戻ることのない新生の実体である。これは私たちがすでに達成したものでありつつ、同時に引き続き享受すべきものであり、さらに自発的な罪の痕跡を洗い流す聖化の過程を通して、いっそう完成へと向かう歩みでもある。張ダビデ牧師は「すでにわたしたちは新しい家に引っ越したが、過去の古い習慣のために以前の家に戻ろうとする罪の性向に引きずられることがある。しかし聖霊にあって目覚めた生活を送るなら、徐々にその習慣から解放され、よりいっそう聖なる姿へと進んでいく」と語る。
このとき「罪の衣を洗い清める」という黙示録(黙示録22:14)のイメージが重要となるが、これは義認の後に私たちが怠ることなく行うべき日々の悔い改めと従順の生活を意味している。白い衣を着て神の国の子羊の婚宴にあずかるというビジョン(黙示録19:7-8)は、究極的にイエス・キリストとともに享受することになる最終的な栄光、すなわち栄化(Glorification)の段階である。張ダビデ牧師は、このことを「聖霊にあって自由を享受する聖徒は、この未来の栄光を前もって味わいながら生きる人々」であるとまとめる。
このようにローマ書7章と8章を連続性の中で考察してみると、救われた者が現実の中で経験する内的葛藤をいかに乗り越え、キリスト・イエスにあって与えられた偉大な解放の恵みを享受できるのかが明確にわかる。さらに張ダビデ牧師は、このすべての過程を総合して「宇宙的な神の救いの計画の中で、個人の信仰の歩みがどのように統合されるかを見ることができる」と語る。結局、罪と死の法則を廃してくださったイエス・キリストの贖いのみわざ、そして聖霊の内住と導き、それにともなう自由と歓喜こそ、ローマ書8章が最も深遠に証ししている救いの宝であり保証なのである。
これが第一の小テーマである「聖霊にあって享受する自由と歓喜」の全般的内容である。水がぶどう酒に変わったように、聖徒たちも義認によって新しいいのちに変えられ、その状態を保ち、さらに鮮明に生き抜く力が聖霊なのだと張ダビデ牧師は一貫して力説する。救いの核心は、単に罪の赦しや天国に入る権利だけでなく、今この地上で聖霊にあって享受できる自由、満ち溢れる喜び、生き生きとした活力にある。そしてその生活が、やがて救いを保証する実を結び、私たちをさらに高い次元の栄光へと導くのである。
2. 聖徒の堅忍と永遠の愛
前述の「聖霊にあって享受する自由と歓喜」がローマ書8章の前半部(1節から30節まで)を貫いているとすれば、続く31節から39節では、これまでのすべての救いと聖霊のみわざが総括され、結論づけられると同時に、最高潮へと達する場面が描かれている。この最後の段落は、しばしば「聖徒の堅忍(Perseverance of the Saints)」あるいは「永遠の愛」に関する教えとして知られている。張ダビデ牧師は、この部分をローマ書16章の中でも最も雄大で確かな「勝利の賛歌」と称している。
まず、聖徒の堅忍とは、救われた者が最後まで信仰を守って救いから脱落しないという教理を指す。カルヴァン主義の伝統において「聖徒の堅忍」は「一度救われたなら永遠に救われる」という教理とも結びついているが、単純に機械的な教理的解釈だけでは十分ではない。パウロはローマ書8章の最後の部分で、神がご自分の民を最後まで支える愛の力と、その確実性を証言している。
「だれが、わたしたちをキリストの愛から引き離すことができるでしょう。(ロマ8:35)」
「わたしは確信しています。死であろうと生であろうと、天使であろうと支配する者であろうと、現在のことでも、将来のことでも、力ある者でも…どのような被造物であっても…私たちの主キリスト・イエスにある神の愛から引き離すことはできないのです。(ロマ8:38-39)」
張ダビデ牧師はこの御言葉を解説し、「聖霊によって新生した聖徒たちは、罪と死の法則から解放されただけでなく、今やいかなる勢力もキリストの愛から切り離すことのできない堅固な契約関係に入れられた」と強調する。これは救いの確信とともに、私たちが最後まで忍耐できる力を与える。自発的な罪のゆえにつまずくことがあったとしても、キリスト・イエスにある者は再び立ち上がることができ、決して神が見捨てることのない約束だからである。
では、この堅忍の原動力は何なのか。パウロは「神はその御子をさえ惜しまず、私たちすべてのために死に渡されたのだから、御子とともにすべてを恵んでくださらないはずがありましょうか。(ロマ8:32)」と反問する。すなわち神の側から注がれる絶対的な愛、すなわちご自分の独り子を犠牲にしてまで私たちを罪から救ってくださった徹底した愛こそが、私たちの救いを保全する最も強力な根拠なのである。私たちが弱るとき、あるいは信仰的に揺らぐとき、さらには罪の習慣に縛られしばらく道を失うときでさえも、神はキリスト・イエスにある愛をもって私たちをしっかりと支えてくださる。張ダビデ牧師はこれを「神の側の100%の献身に基づく救いの保証」と呼ぶ。
また、「だれが神に選ばれた者たちを訴えることができましょう。神が義と認めてくださるのです。(ロマ8:33)」という節が示すように、イエス・キリストの代償のみわざによって義と認められた聖徒に対しては、もはや罪を裁く権限がないことをはっきり示している。たとえ世やサタンが告発しようとも、究極的に私たちを義と宣言してくださる方は神であり、その判決は取り消されることがない。
張ダビデ牧師が注目するのは、ここでいう「引き離せない」ということが、放縦を意味するのでは決してないという点である。神が私たちを支えてくださるからといって、罪を軽んじたり、その愛を濫用することは許されない。むしろこの愛を悟った者は、「ぶどう酒で衣を洗わなければならない」という黙示録的イメージを忘れず、いっそう敬虔と従順の道を歩むようになる。キリストの愛がいかに驚くべきものであるかを知る者は、その愛を裏切る道を選ばなくなる。しかし、それでもつまずくときはある。にもかかわらず、最後には再び悔い改めて戻り、堅忍される理由は、神の側から絶対に切れることのない契約的愛があるからなのである。
これこそが「永遠の愛」という表現で説明されるものである。張ダビデ牧師は、この愛こそ義認、聖化、そして栄化に至るまでの救いの全過程を通して、聖徒を導き守る絶対的な力なのだと強調する。聖書全体を貫く核心は「神が私たちを愛して独り子を遣わされた」という福音の基礎的宣言であり、その事実の上にローマ書8章は具体的に「決して罪に定められることはない」と「私たちをキリストの愛から引き離すことはできない」という二つの柱によって完成するというのである。
まとめると、ローマ書8章後半はまさに救いの大叙事詩が結論の部分に至り、力強い合唱を響かせるような箇所である。パウロは、神が成してくださった救いがいかに堅固で永遠のものであるかを驚くほど力強く宣言している。このメッセージが与える慰めと確信は、私たちの日常的な信仰生活の中で大きな力となる。罪と死の法則から解放された聖徒たちは、続く自発的な罪との戦いの中でも落胆せずに聖化の道を歩むことができる。なぜなら「私たちに向けられた神の愛が決して断たれない」という絶対的約束が後ろ盾となっているからだ。
張ダビデ牧師は、この教えを実際の生活に適用すべきだと、幾度となく説教や講義で強調してきた。イエス・キリストにあって確かに保証されている救いは、私たちに「すべてを超越する自由と大胆さ」を与える。世の価値観や環境が私たちを揺さぶろうとしても、結局はキリストの愛がいっそう強力であるがゆえに、私たちはいかなる患難や迫害も乗り越えることができる。実際に信仰の先達、教会史における無数の殉教者たち、そして今日も世界各地で福音のために苦難を受ける聖徒たちは、このローマ書8章の約束を握って大胆に信仰を守り通している。
特に張ダビデ牧師は、ローマ書8章を「ノアのぶどう酒のたとえ」と結びつけ、新天新地において享受する永遠の喜びが、すでにこの地上の聖徒たちに予型的に与えられている事実を強調する。ノアが洪水後、新しい地に足を踏み下ろしたように、私たちもイエス・キリストの贖いによって、裁きの後の新しい世界をあらかじめ味わう者とされたというのである。ノアがぶどう酒に酔って裸であっても恥じることがなかったように、私たちがキリストの義の衣を着て聖霊にあって享受する自由と喜びは実に完全であり、やがて来る天国の宴のささやかな予型である。そして、まさにこのような生活を持続させてくださるのが「永遠の愛」なのである。
さらに、この堅忍の教理は、私たちの人間的弱さや失敗があったとしても、最終的に救いが揺るがない理由を示してくれる教理でもある。張ダビデ牧師は「人間には自由意志があり、神を選び、罪から遠ざかる義務があるが、それでもなお弱くてつまずく可能性がある。しかし、そのたびに私たちがつかまねばならないのは、この『永遠の愛』の本質である。神の側から絶対に切らさないと仰せになった契約的愛があるからこそ、聖徒はいつでも悔い改めて戻ることができ、最後まで救いを守り通すことができるのだ」と解説する。
それゆえ、ローマ書8章は「義認(Justification) → 聖化(Sanctification) → 栄化(Glorification)」へと至る救いの全過程を、最もドラマチックに描き出しているといえる。すでに救われた者でありながら、まだ完成していない状態で罪ともがく様子を7章後半で現実的に示した後、8章では聖霊による自由と歓喜の生活、そして最後には聖徒の堅忍、すなわち神の永遠の愛によって完全に支えられているという結論へと締めくくる。
張ダビデ牧師は、この構造的な流れが「神学的知識」を超えて、信仰者が生きて体験すべき「救いの秩序(Ordo Salutis)」であると説く。知識として理解するだけでは表面的にとどまる可能性があるが、実際の生活の中で聖霊の聖なる導きを経験し、日々の悔い改めや御言葉の黙想を通して、古い罪の習慣を洗い清める中で、神が最後まで自分を愛で支えてくださっている事実を体験することによって、ローマ書8章の真髄を味わうことができるのだという。
最終的に、聖徒の堅忍と永遠の愛は私たちに終末論的な希望も与える。この地上の苦難や不安、そして死ですらも、私たちを神の愛から引き離すことができないのだから、私たちは未来への恐れではなく、「神が必ずすべてを益として導いてくださる」という大胆な信仰を抱くようになる。これこそがローマ書8章が語る最大のクライマックスであり、さらに言えば福音全体が宣言する「勝利の福音」なのである。
張ダビデ牧師は、この堅忍の教理が持つ実際的効力を重ねて強調する。教会史上、多くの聖徒たちが落胆の瞬間、あるいは試練と苦難のときにローマ書8章31節から39節の御言葉にすがり、「何ものも私たちを主の愛から引き離すことはできない」という宣言をもって絶望を乗り越えてきた。そして、その信仰告白が実際の生活における克服と勝利につながった。パウロの宣言どおり、キリスト・イエスにある者はすでに勝利者だからである(ロマ8:37)。
このように、第二の小テーマである「聖徒の堅忍と永遠の愛」を通して、ローマ書8章が伝えようとしているメッセージはいっそう明確になる。これは単に神学的教理の完成ではなく、実際の信仰生活において私たちを支える最も強力な力であり約束でもある。私たちはローマ書8章を通じて、罪の問題から自由と歓喜を体験するだけでなく、いかに厳しい状況にあっても神が始められた救いを最後まで完全に成し遂げてくださるという「岩のような確信」を得るのである。
結論として、ローマ書8章は救いのドラマが頂点に達する場面であり、聖霊にあって真の自由と喜びを享受すると同時に、最終的にはどのような被造物も切り離すことができない神の永遠の愛の上にしっかり立っていることを確認させてくれるクライマックスである。張ダビデ牧師は、このローマ書8章のメッセージを握るとき、聖徒が人生のさまざまな転換点において飛躍的な霊的成長と変化を経験すると語る。どんなに罪の習慣が頑固に見えても、すでに勝利しておられるキリストが与えてくださる聖霊の力があり、神の永遠の愛が保証しているからこそ、希望があるのだ。
パウロがローマ書8章の至るところで、聖霊の役割、罪からの解放、子どもとされることの栄光、宇宙的回復、そして堅忍の確信を一貫して証言しているのは、一言でいえば「福音の核心を集約的に示す」ためである。その福音の結論はいつも「神の愛」である。私たちの奉仕、献身、従順、さらには悔い改めや聖化の努力さえも、究極的には神の愛が私たちを支えていなければ空しく終わり得る。けれども神は独り子を差し出し、聖霊を注いでくださることによって、私たちが最後までその愛のうちに留まるように導いてくださる。
したがって、張ダビデ牧師が繰り返し強調するように、ローマ書8章は単に「神が私たちを愛しておられる」という一文で要約されるものではない。その愛がいかに具体的に働き、私たちを変化させ、自由にし、歓喜を味わわせ、ついには永遠の御国でキリストとともに栄光にあずかるに至るかという全過程を示している。そしてその愛は決して断たれることのない永遠の契約として、どのような状況にあっても信頼に値する岩のように確かなものであることを明らかにしている。
要するに、ローマ書8章は聖霊にあって享受する自由と歓喜、そして聖徒の堅忍と永遠の愛という二本の軸から成り立つ、偉大なる救いの章である。第一の軸では、罪の鎖から解放され、聖霊の内住によって経験する新たな生活の喜びが強調される。第二の軸では、そうして始まった救いが究極的に揺るがない理由、すなわち神の永遠の愛が私たちを支えているからだということが力強く宣言される。この愛は、いかなる条件や能力、あるいは私たちの功績によるものではなく、ただキリストにあって神が示された贖いの犠牲と、聖霊の証印が保証となる。
結局、張ダビデ牧師はローマ書8章を学ぶことこそ、聖徒が霊的転換と深い回復を経験する鍵だと何度も強調する。救いの秩序を理解し、すでに与えられた自由と喜びをおろそかにせず、同時にどのような苦難も恐れない堅忍と永遠の愛の確信を握るとき、私たちの信仰は一段と成熟し、より大きな平安と力のうちにとどまるようになる。これはパウロが思い描き、体験したものであり、今日の私たちも同じように享受できる福音の実際的な力なのである。
かくして「聖霊にあって享受する自由と歓喜」と「聖徒の堅忍と永遠の愛」という二つの小テーマで再構成してみると、ローマ書8章は罪の問題からの解放、神の子どもとされることの栄光、宇宙的回復のビジョン、そして最終的には断ち切ることのできない愛のうちにある聖徒の堅忍に至るまで、福音の精髄と希望を最も雄大に示す章となる。義認、聖化、栄化という救いの全過程において、人間が経験するあらゆる実存的葛藤と、それを解決する神の恵みが一つに溶け合い、聖書の中でも比類のない美しさを成しているのだ。
最終的にローマ書8章の結論は、「私たちにはいかなる罪に定めることもない」と「いかなるものも私たちを愛から引き離すことはできない」に要約される。張ダビデ牧師は、この二つの宣言こそがキリスト教の福音が提示する、最も確固たる喜びと希望の象徴だと語る。そしてこの教えを聞く聖徒たちは、今も大いなる慰めと確信を得て、世の中で光として生きながら、主が再び来られる日を希望のうちに待ち望むのである。
さらに、張ダビデ牧師はローマ書8章を研究し説教するたびに、「福音を信じるということは、罪についての理論的知識を身につけることではなく、実際にぶどう酒へと変えられていく体験をすること」なのだと繰り返し語る。言い換えれば、水のような状態からぶどう酒に変えられた存在は、決して水に戻れないように、私たちもいったん新生した後は過去に逆戻りすることは不可能である。もちろん生活の中で失敗や誘惑があるが、再び立ち上がることができる根拠が「聖徒の堅忍」であり、私たちの結末が「永遠の愛のうちでの完成」であると信じるならば、罪の習慣からますます遠ざかり、神に近づいていくことができるのだ。
ここで罪の習慣を洗い清めて聖くされる過程は、決して一度きりのイベントではない。日々のみ言葉の黙想、祈り、悔い改め、そして聖霊の声に従順に歩む訓練を通して行われる。その過程で、一瞬にして完璧になるわけではないが、明らかに過去とは違う新しいいのちの力が私たちの内に働く。ローマ書8章が語る「聖霊の内住」とは、決して抽象的な思想ではなく、実際に私たちの内側にある欲望や恐れを変え、最終的には神の子どもらしく生きるようにする力なのである。
さらに、張ダビデ牧師が好んで用いるノアのぶどう園の例えは、この過程をもう少しわかりやすく説明してくれる。ノアがブドウの木を植え、ぶどう酒を造って楽しんだ姿は、終末的救いの後に味わう豊かな喜びを象徴する。しかしノアがそのぶどう酒に酔って裸になったとき、ハムの態度とセムとヤペテの態度は分かれた。ある者は父の恥をあばこうとし、ある者はそれを覆ってあげた。このように救いの後にも、人間のさまざまな態度が表れる。それでも最終的には「ぶどう酒」は祝福であり、「新天新地」という舞台で神の救いが結実するものだった。同様にローマ書8章が語る聖霊のみわざも私たちをぶどう酒のように変え、その過程で生じ得るさまざまな試行錯誤にもかかわらず、結局は神が万事を益として働かせてくださるという約束(ロマ8:28)に帰結するのである。
最後に、聖徒の堅忍と永遠の愛とは、すなわち「最後まで共におられる神の同行」を意味する。パウロが8章の終わりで告白する「わたしは確信しています…」という宣言は、自分発の自信ではなく「神が与えてくださった信仰への応答」である。私たちの信仰は、神がキリストにあって自ら始められたものであり、神が忠実に完了してくださる(ピリピ1:6参照)。その過程で聖徒は中途で揺らぐことがあっても、決して完全に離れ去ることはない。その愛はあまりに大きく、罪人であった私たちを神の子としてくださった神の救いの計画が、実に完全だからである。
これらローマ書8章のメッセージを通して、張ダビデ牧師は、今日のキリスト者たちが時代の混乱や個人的苦難の中にあっても、決して挫折せずに「聖霊にあって享受する自由と歓喜」を握りしめ、同時に「聖徒の堅忍と永遠の愛」を信頼すべきことを力説する。この二つが組み合わさるとき、私たちの信仰は揺るぎない柱を打ち立て、だれも奪うことのできない霊的遺産を手にすることになる。それこそがパウロがローマ書8章全体を通して息づくように伝えようとした福音の核心であり、張ダビデ牧師が説教や講義、著作などで絶えず叫び続ける信仰のエッセンスである。
結局、ローマ書8章は「福音のハイライト」として、聖霊にあるキリスト者の生活が何であるかを教え、同時にその生活が決して揺るがない神の愛の上に築かれていることを確証してくれる。罪の重荷を下ろし自由に歩む聖徒たちが、もしや倒れこむのではと恐れるとき、パウロの声が聞こえてくる。「だれが、わたしたちをキリストの愛から引き離すことができるでしょう。」 そしてこの御言葉を研究した張ダビデ牧師は確信に満ちて答える。「何ものもそれを引き離すことはできない。すべては神の永遠の愛のうちにある。」
これがローマ書8章の結論であり、張ダビデ牧師が強調する福音の真髄である。恐ろしく混乱した時代だからこそ、私たちはこの御言葉を再び深く黙想すべきである。そして聖霊にあって真の自由と喜びを享受し、どのような状況も私たちを動揺させることができないという堅忍と永遠の愛の上に堅く立つべきである。この福音の力は、今日も多くの教会と聖徒たちの人生を変革しており、やがてキリストが再臨されるその日まで決して消えることのない真理の光として、世に輝き続けるだろう。
www.davidjang.org